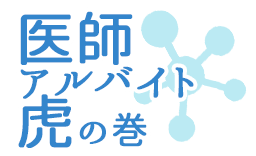薬剤師
薬局や病院で調剤を担当する専門職
薬剤師は病院や調剤薬局で医師の処方箋を元に必要な薬剤を調剤するための仕事です。
従事するためにはまず国家資格を取得しなくてはらならず、全国にある薬科大や薬学部に進学をし6年間のカリキュラムを経て国家試験を受験します。
薬剤師の試験制度は以前までは4年制だったのですが、近年急速に高度化している薬剤医療に対応するべく、医師や歯科医師、獣医師などと同じく6年制に変更になりました。
現在ほとんどの大学で対応がされていますが、中にはまだ未対応のまま4年制の薬学部も存在しています。
そうした4年制薬学部を卒業しても薬剤師の受験資格がありませんので、別の大学に編入をするなどして対応する必要があります。
薬剤師の国家試験に合格をすることで厚生労働大臣から免許が発行されます。
試験は毎年3月上旬の2日間をかけて行い、必須問題試験と一般問題試験をそれぞれ筆記試験で受験します。
医療系の国家資格のほとんどは受験資格が特定の大学や専門学校での課程の修了となっています。
しかし薬剤師はそうした資格の中でも非常に試験の難易度が高く、医師免許や看護師免許資格が90%を超える合格率であるのに対し、薬剤師は60%台にとどまっています。
これは制度の移行の過渡期であることもありますが、人材的に薬剤師資格が過剰状態にあることも関係しています。
調剤薬局や病院からの薬剤師求人の数はそれほど多いものではありませんので、今後は薬剤師資格のある人材はドラッグストアや民間の製薬会社など幅広い業界に進出していくことが多くなりそうです。
実際、薬剤師の専用の求人を見ても、以下のようにドラッグストアや製薬会社などの募集が年々増えています。
このように、今後もより薬剤師のロイヤリティは上がっていくことでしょう。
今のうちに薬剤師の資格を取得し手に職として身につけるのもいいではないでしょうか。
医療施設における薬剤師の役割は高まっています
人材が過剰気味になっている一方で、医療現場で仕事を行う薬剤師の責任は年々高まる傾向にあります。
これはかつての薬剤師は医師が出す処方箋の内容を忠実に調剤するという事務的な仕事であったことから、より主体性のある業務へと転換したことが関係しています。
患者さんに処方する薬剤については基本的には処方箋に従うものの、患者さんの体質や過去の薬歴などをもとに、どういった出し方をするのが最もよいかということを薬剤師自身で考えていくことができるようになりました。
例えば小児科での処方においては、粉薬や錠剤、飲み薬などといった種類の中から最も適したものを選んだりといったような感じです。
欧米諸国においては「医薬分業」がしっかりしており、より薬剤師の役割や責任は重くなっています。
日本においてもそうした欧米諸国の実態に近い、薬剤師の権限の大きい制度へとなっていくことが予想されます。
また女性の資格者が多いことも特徴で、患者さんの様態を聞きながら薬を考えるコミュニケーション能力も求められる資質と言えます。