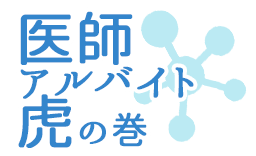診療放射線技師
診療に必要な放射線を専門に扱う技師
診療放射線技師は、医療技術の進歩に伴い治療に積極的に使用されるようになった放射線機器を専門に取り扱う仕事です。
以前までは「X線技師」と言われていた仕事だったのですが、1968年からはX線以外の放射線であるα線やβ線なども診断や治療に用いられるようになってきたため「診療放射線技師」と名前も新たに法律が制定されました。
1993年以降はさらに磁気鳴動画像診断装置や超音波診断装置、眼底カメラ検査といったような高度な機器も加わり、年々診療放射線技師の業務範囲は拡大する傾向にあります。
「放射線」と聞くとどうしても原子力発電事故のイメージがあるためか、何だか恐ろしいもののように考える人もいますが、医療機器に使用する放射線は非常に便利な技術であり医療技術一般を大きくレベルアップさせるものです。
そのため診療放射線技師をとりまとめている公益社団法人日本診療放射線技師会では、患者さんの不安を取り除き放射線がどのようなしくみで治療や診断に用いられているかということを詳しく説明する活動を行っています。
診療放射線技師はそうした取組みを受け、患者さんに説明をするとともに正しく事故の起こらないよう放射線医療機器を使用していく義務があります。
診療放射線技師の資格取得と具体的業務
診療放射線技師は国家資格であることから、就業前に試験に合格をしなければいけません。
受験資格は専門課程のある大学や専門学校、養成所といったところで必要単位の履修をすることで、学校卒業時に年一回行われている国家試験を受けます。
国家試験では基礎医学の他、放射線生物学や放射線物理学など幅広い分野から出題がされることとなっています。
合格率は約73%で、他の医療関連資格と比べるとやや低めな印象です。
2008年の厚生労働省の調査によると、病院や診療所で診療放射線技師として勤務している人は約4万6115人とされています。
比較的安定的な仕事で離職率も低めなのですが、年々高度化する医療機器への対応は難しく人材はやや不足がちです。
診療放射線技師として勤務をしていくときには、常に新しい技術について勉強をし病院で導入できるようにする姿勢が求められます。
放射線を用いた治療・検査は、レントゲン撮影や消化管臓会検査、乳房撮影(マンモグラフィ)、核医学検査、CT検査、MRI検査、血管検査、超音波検査、骨密度検査と非常に多岐にわたります。
さらにがんの治療で重要な役割を担う放射線治療も診療放射線技師の担当となりますので、病院内のみならず社会的に責任の大きな仕事と言えます。
放射線という高度な物理の知識を伴う理系の職業ですが、意外に女性の就業者が多く見られることが特徴です。